
第1章「ロイヤルウェディング」 8話
担当:幻灯夜城
その甲冑の腕に捲かれた腕章。それはまさしく――当然なのだが――ルーシフ王国のものであるということ。何度見てもその結果は覆ることはなく、それが目の前に在ることそれ即ち男の逃亡劇の最大の難関が目の前に立ちはだかったことの証明に他ならなかった。
ここまで来るといっそのこと清々しささえ覚える。神様なんてこの世にはいない。自分の窮地を救ってくれる頼れる仲間とか、つらい時に隣にいてくれる友とか、そういう純粋な空想(モノガタリ)はティーンエイジャーにのみ許された逃避の権利。今この場、この瞬間においては逃避する思考も出来ず、目の前の現実を直視するしかない。いや、前提からして。
そもそもこんな世界に、救いはあったのだろうか。
「何をしていると、聞いている」
淡々と、しかし威圧を込めて兵士は言葉を反復する。押し黙った彼らへと向けて早く口を開け、あるいは自分の仕事を長引かせるんじゃないと鬱憤をぶつけるように、問いかけてくる。決して赤子に対するものではない。答えをしくじれば一発縛り首だってありうるかもしれない。
低く、冷たい目で見下ろす兵士へと男は見上げるような形で媚びを売った。
「旦那、ここは見逃していただけませんでしょうか?」
「お前が答え次第では見逃してやる。早く言え」
「いえ、私も忙しいんですよ。借金取りに追われて夜も眠れないもので」
言うなり、おもむろに男は自分の「収穫」の入った袋に手を入れた。そして取り出したものをすばやく、そっと、兵士の手の平に握らせた。陽が当たることのない、影にある金貨数枚。どれもこれも、先の店の店主からかっぱらってきたもの。
そしてそれを見ていたウィリーゼはその行為が何を意味するものかを悟ってしまった。悟ってしまった上で――口に出そうとして、塞がれた。
「むぐぅ!?」
「――まぁ、これで失礼します」
「……そうだな。特に異常はないようだ」
男はウィリーゼの手を引っ張り路地裏へと消える。
兵士は何食わぬ顔で彼らを見送る。何も異常はない、「そういうこと」にされたのだから異常はあってはならないのだ。もしくは他の異常を捕まえる、あるいは手柄立てるついでに通常を異常に仕立て上げて捕まえなければならないのだ。
男は兵士の目が完全にこちらから外れる所まで動き、ようやくその手を離した。
「ここまでくりゃ、追って来ないはずだ」
安堵する。今日も生き延びられることに、そして名も知らぬ少女を巻き込まなかったことに対して、この神のいない世界に感謝の念を捧げるのを忘れない。
「あの」
「何だ?」
何かを言いたげなウィリーゼの視線が男に突き刺さる。
今更、罪悪感を覚えるつもりもないが、純真無垢であろう少女の咎めるような視線というのはどうにもこうにも、慣れないものである。
「さっきのあれ、賄賂、ですよね」
「知ってんのか。親から教えてもらったのか?」
「本で読みました」
ついうっかりしてしまうと「小さいのによく色んなこと知ってるな」と言いそうになるが、仏の顔も三度まで、出かけた言葉を喉奥にしまいつつ出来るだけ、出来るだけ軽い調子で意地の悪い質問を投げかける。
「で、どう思った?」
「どうって、……」
答えられるはずがない。
男は幾ら十七でも泥沼に腐りきった現実を直視するには速すぎると考えていたのだから。
少女は自国の兵の実態を把握していなかったことにショックを受けていたのだから。答えに窮し、黙り込んでいたウィリーゼに、更に重ねるようにして冗談めかして笑った。
「いや、いい。答えられないわな。
悪いことだろうよ。でも、これが生きる術だってこともある。
むかーし、どっかの国で逮捕された大物政治家だって賄賂を繰り返してきた。俺が今やったのは、それに比べればちっぽけだが……悪なんだろう、きっと」
悪だ。そう言いたかった。でも言えなかった。
確かに、それは悪だ。だが、仕方のないことであるはずなのだ。そうでなくてはあまりにも非情過ぎやしないか。
沈みかける夕日。
陽の射さぬ裏路地。だんまりになってから、どんよりとした空気が漂い始めた男女の影。
「悪い、喋りすぎた。俺はもう行く。次見つかれば多分ただじゃすまねぇだろうし、顔も割れちまったからな」
「あっ……」
男はそのまま早足で何処かへ去っていく。
呼び止めることも出来ずに、ウィリーゼはその背中へと伸ばしかけた手を、ゆっくり、ゆっくりと引っ込めるしかなかった。




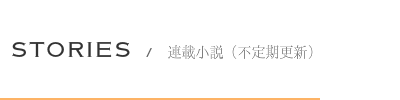
 前話
前話