
第1章「ロイヤルウェディング」 4話
担当:榎本かほり
王宮の警備網を知り尽す王女は人目を盗んで庭園を駆け抜け、 そっと城壁の前に立つ。
たくさんの蔓の奥に隠されたそれは、ヴィリーゼだけが知る隠し扉。葉を掻き分け、現れた石壁をそっと押せばそれはどんでん返しのように回転して王都へ続く道を示し出しす。
ヴィリーゼは慣れた手つきで扉をくぐり抜けると、あっという間に城を脱出していた。そして木漏れ日が彩る、斑点模様の砂利道を鼻歌交じりに歩いていく。
一国の王女は毎日のように城を抜け出してはこのスリリングな散歩を楽しんでいた。
育ち盛りの女の子が日々厳粛な場に身を置き、王女としての優美な立ち振る舞いを強いられるのは少々狭苦しい。城を抜け出すことは彼女なりの最大限の反抗であり、唯一の息抜きだった。
林を抜け、視界が開けたその先でヴィリーゼは王都を一望する。
「ふう、今日も絶好のお散歩日和ですね」
そう呟く彼女の目はキラキラと輝いていた。
目の前に広がるは活気付いた、いつものヴェンツェーヌ王国の風景。彼女が最も愛する景色だった。
お忍びで行く王都は何度訪れても新鮮に映った。
ヴィリーゼは金色の髪をなびかせながら、大市(おおいち)に売られた商品をしげしげと眺める。新鮮な果物に、焼きたての菓子、色とりどりな花草に、独特な骨董品。外来商人らも出品していたこともあって、その中には彼女も見たこともないようなモノもたくさん売り出されていた。
「いいなあ」と、市場を歩きながら彼女は思う。
王都にいる全ての民が自分より輝いて見えた。周囲を見回せば、自分と変わらない年頃の子供たちも、無邪気に駆け回っていた。彼らとは違い、変えられない自身の運命が、御国の為とはいえ数日後に迫る結婚式がヴィリーゼは嫌で仕方がなかった。
すると少女は、ある一つの店の前で立ち止まった。
質素なパン。
香ばしい匂いが彼女の食欲をそそり、そういえば今日まだおやつを食べていないことに気が付く。ヴィリーゼは王宮の豪勢な食事も好きだったが、こういった庶民の味も好みだった。
買うか買うまいか悩む最中、突如、凄まじい衝撃がヴィリーゼを襲う。
「きゃっ」
ヴィリーゼは耐えきれずに倒れ込むと、彼女と同様に尻餅をつく男がいた。
「いってぇー」
そう呟く男は、ヴィリーゼもよく知る異国の服を着ていた。




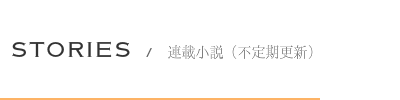
 前話
前話