
第1章「ロイヤルウェディング」 6話
担当:小豆
ぽかんと男の口が空く。
盗人の手助けをし、物騒な罵声を吐く追っ手から命辛々逃れたこの状況を、目の前の少女はこともあろうに「楽しい」と笑顔で言ってのけたのだ。
胆力があると言えば聞こえは良いが、スリルを求めるならもう少しやり方があるだろうに。犯罪者である自分に手を貸すことがどういうことか、一歩誤れば命すら危うくなるということが、この上品な娘には分かっているのだろうか。
分からない。男がヴェンツェーヌ王国に来て久しく経つが、こんなことは初めてだった。異国の、決して見なりも良くない自分の手を取る人がいたなんて。
「……アンタ、変な奴だな」
出稼ぎにこの国へ訪れて、けれども仕事はうまく行かず挙げ句の果てには盗みに手を染めた。そんな男に、少女の手は久方ぶりの人の温かみを思い出させてくれるような気がして。
もっと気の利いた言葉か感謝の言葉のひとつでも出てくればいいのだが、生憎と男の語彙力には限界があった。
「私は民……じゃなくって! 困っている人を、放っておけないだけです」
それでも、ふわりと香る花のような微笑みを浮かべてくる少女が、男には酷く眩しいものにみえて。同時に、彼女を巻き込むわけにはいかないと一層の決意を固めさせる結果となった。
「…さて、助けてくれてすまねえな。俺はもう行く」
「行くって、どちらにですか?」
「逃げるんだよ。捕まったら俺ぁ殺される。嬢ちゃんはさっさと帰んな」
「! 嫌です!」
路地の奥へと進もうとした男の行く手に少女が立ち塞がる。
「スリルならもう味わったろ、そこどいてくれ」
「私も一緒にお手伝いします!だって、お金を盗む理由があるんでしょう?」
「危険だ。あんたまで殺されちゃ寝覚めが悪くて仕方ねえ」
「わ、私だって自分の身位は守れます!」
脇をすり抜けようとしても、先程の逃走劇を繰り広げただけあって少女は随分と機敏だ。フェイントの応酬が何度となされるうち、男の痺れが切れてくる。
「ガキは家に帰ってママのお手伝いでもしてるんだ!」
ついに声を荒げ、男はビッと逃げてきた道を指さす。両者が一瞬動きを止め、静寂が広がった。
見れば、言葉に少女の頬がみるみるうちに膨らんでいくではないか。
「私は! もう17です!!」
「…………えっ」
思わず零れた驚きの声は、随分と間の抜けたものになってしまった。17といえば、人によっては嫁に行く可能性もある年齢、立派な大人の一員だ。
しかし、仁王立ちで眉を吊り上げる少女は男の胸元辺りまでの背丈しかない。大きな青い目が輝く顔立ちは大人と呼ぶにはあまりにあどけなく、おまけに反らしているにも関わらずその胸は、何というか。
「……ちっさ。」
たった一言、呟くような感想が少女への印象を全て物語っていた。
それが雷に打たれたかのような衝撃なのだろうか。文字通りそのような表情を浮かべ、少女の小さな拳がぎゅうと握りこまれる。
「ち、ちっちゃいとか言わないでくださいっ!」
「あ、悪ぃ悪ぃどー見ても10歳くらいにしか見えねえもんだから……あ、」
それが地雷であると男が気付いた時には既に遅く。少女のワンピースに包まれた小さな肩はふるふると震え、大きな瞳には零れそうなほどに涙が溜まっていく。
「ち、ちっちゃくなんか、ちっちゃくなんか……むねぺったんでもないもん……もん……ぐすん」
「わ、悪かったって! ほら嬢ちゃんそんなに泣くなよ? なっ?」
慌てて背を屈めて目線を合わせた男の慰めは、果たして聞こえているのだろうか。
少なくとも、涙を堪える姿も含めやはりどう見ても幼子にしか見えない少女を泣かせてしまった罪悪感が、彼女を放置して逃げるという選択を男から奪っていったことは確かなようだ。




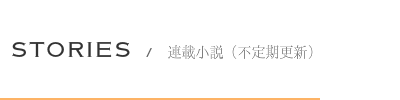
 前話
前話