
第2章「知らないセカイ」 4話
眠りのなかで妙な既視感を覚えることがある。
けれどそれがどんなものだったのかは思い出せない。
ただ、目を覚ますと溢れ落ちる温かい涙だけがその懐かしさを物語っていた。
「……え。ねえってば」
暗闇の中、遠くから女の呼ぶ声がする。
どこかで聞いたような優しい声。
その声に誘(いざな)われるようにして、陽介の意識は深い泥沼からそっと掬(すく)われた。
ゆっくりと目を開けた。微睡む直後、針のように突き刺さる日の光で現実に引き戻される。重い上体を起こして辺りを見渡すが、周りには先程の声の主どころか誰ひとり側にいない。かわりに視界に飛び込んできたのは先程までいた大会会場とは違う、全くの知らない景色だった。
「ここは、どこだ?」
陽介は小さく声を漏らす。
そこは現実味のない草原だった。金色(こんじき)に染まった草花が生い茂り、樹木は鬱蒼(うっそう)と繁茂(はんも)している。萌え出たばかりの若葉は金色に縁取られ、垂れた花房(はなぶさ)は黄金の炎ように枝から垂れていた。
眩しかった。思わず目を細めてしまうほどに、その草原は輝いていた。
なんでこんなところにいるんだろう。陽介は考える。記憶を遡るものの、こんな場所に来た覚えはない。それどころかプールで気を失ってからの記憶が全くなかった。
(――あれからどうしたんだ? 試合は? みんなは?)
いつの間にか服を着ていたが、身体はまだびっしょりと濡れていた。少し塩素の匂いがする。あの試合からそう時間が経っていないのは間違いないようだ。
しかしどれだけ思考を巡らそうと肝心の答えは出ない。考えれば考えるほど陽介の頭は割れるようにズキズキと痛んだ。
「あら、ようやくのお目覚めね」
しばらくして遠くから女の声がした。
陽介は驚いて振り返る。
そして思わず、
「え、あ、彩香さ――」
そう言いかけて、やめた。
木々の茂みから現れたのはヴェールを纏った見知らぬ女だった。それは逢坂彩香のようで逢坂彩香ではない。声も背格好も彼女にそっくりだったが、その風貌はどこか人間離れした、神聖的ななにかを感じさせた。
「よかった、思ったより元気そうね。あなたを見つけたときは本当に驚いたのよ。何度呼びかけても反応がないからもう手遅れかと思っちゃった」
立ち上がっている陽介を見て女が安堵したように言う。
「じゃあ、もしかしてきみが僕を助けてくれたの?」
「そうよ」
女はそう答えて近くの池を指差した。そこから陽介をほとりまで引っ張り上げたという。
「な、なら教えてくれよ。あれから試合はどうなった? みんなは? きみなら何か知っているはずだろう」
焦る心を抑えきれず、陽介は礼を言うのも忘れて矢継ぎ早に質問をする。そんな彼を見て女は首をかしげた。
「何のこと? ここには最初からあなたと私しかいないわよ」
「えっ」
陽介は絶句した。確かに周りには誰もいなかった。葉擦れの音や小鳥のさえずりさえもが鮮明に聞こえるほどに、この草原は静かで孤独だった。
「そんな。じゃあここはどこなんだよ。僕は、さっきまで総合プールにいて、それで、どうして僕はこんなところに……」
「落ち着いて。急いても何も良いことはないわ」
「でも」
「大丈夫」
宥めるように女が言う。その声はとても穏やかで、あんなに高ぶっていた陽介の感情も不思議と静まってしまう。
「私が気付いたときにはもう、あなたはそこの池に浮かんでいたわ。だからそれより前のことは私にもわからないの」
「……そっか」
手がかりを失い、陽介は悄然(しょうぜん)と腰を下ろす。疑問符を頭に浮かべた女に事情を説明すると、彼女は何かを考え込むようにして腕を組んだ。
そして「もしかして」と言葉を零す。
「あなた、この世界の住人じゃないでしょう」
「え?」
陽介は聞き返す。
「ずっと不思議に思っていたのよ。だって突然ヒトが池から浮かび上がってくるなんて、普通おかしいじゃない。けれどあなたが別の世界から来たのなら説明がつくわ」
「ま、待って、どういうこと?」
焦った様子の陽介を見て、女ははっきりと言う。
「どうしてかは分からないけど、あなたが〝違う世界〟に迷い込んできてしまったんじゃないかなって、そう思ってるの」
「迷い込むって、一体……」
女は静かに息を吸う。
「ここはおそらく、あなたのいた場所じゃないわ。ここは『園』っていう一つの空間からできた世界なの」
「ソノ?」
「そう。私のためだけのセカイ。ここの住人はみんな、自分だけの園を持っているの。そうやってたくさんの園が円のように連なって、この世界は成り立っているのよ」
「……」
陽介は目の前にいる女の言っている意味が全く理解できなかった。自分だけの園? 違う世界に迷い込んだ? 冗談じゃない。どこかのおとぎ話じゃあるまいし、そんな突飛なことを言われても簡単に信じられるはずがない。しかし目の前に広がる金色の草原が、いま自分が置かれているこの状況が、明らかに普通でないことは陽介も分かっていた。
「まあ混乱するのも無理ないわ。色々思うことはあると思うけれど、とりあえず、あなたがもといた世界に帰る方法を探しましょう。私も協力してあげるから」
「えっ」
戸惑う陽介の手を女は強く握りしめる。
「大丈夫。ここに来れたんだもの、帰る道も必ずあるはずよ」
彼女の温もりが、じんわりと肌を通じで伝わってきた。
「ど、どうしてきみは見ず知らずの僕に優しくするんだ。僕のことなんてどうでもいいはずだろう」
陽介の問いに女は短く「ふふ、なんででしょうね」と笑って答えた。
「あなたって何だか放っておけないのよ」
その言葉に一瞬、陽介の肩が動いた。
一呼吸置いて、女は「それに」と付け加える。
「この世界は案外居心地いいのよ。帰る方法を探すついでに、いろいろな園を見て回るといいわ」
「……ありがどう」
優しく励まし続ける彼女を見て、陽介は思わず笑みがこぼれた。右も左も分からなかったが、こうして親身になってくれる人がいるだけまだ救われているかもしれない。陽介のなかでずっと張り詰めていた糸が少しだけ緩んだような気がした。
「あ。そういえば、まだあなたの名前を聞いてなかったわ」
突然思い出したように女は声を上げた。
「陽介、だけど」
溢すように名乗ると、女は「ヨースケ、ヨースケね」と噛みしめるように陽介の名前を繰り返した。そして、
「面白い名前ね。私はパーチェっていうの。よろしくね」
そう言ってパーチェと名乗る女は静かに微笑んだ。その不意な笑顔に陽介は頬を赤らめる。彼女の笑顔はヴェール越しでも美しかった。




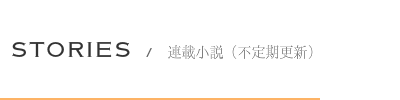
 前話
前話