
第2章「知らないセカイ」 5話
「いい、ヨースケ。この世界には一つだけ守らなければいけないルールがあるの」
パーチェが人差し指を立てて説明する。
「さっき、たくさんの園が連なっているって言ったでしょう? もし園を行き来するときにはこの紲(リアン)っていうものが必要になってくるわ」
そう言って彼女は懐から黄色の細い糸のようなものを取り出した。ちょうど20センチくらいの長さがある。「まあ移動するための切符だとでも思ってくれればいいわ」パーチェはそれを緩く陽介の手首に巻きつけ、蝶結びにした。
「とにかく絶対にこれをなくさないで。これは私とあなたとの親愛の証だから」
陽介は着けられた即席のブレスレットをまじまじと見た。ただの絹糸のように見えるが、一体何が特別なのだろうか。陽介にはまるで分からなかった。しかし「絶対」と強く念を押されると反って気になってしまう。丁寧に紡がれたそれからは仄かに甘い香りがした。
「この紲を使って隣の園にいるキームに会うといいわ。彼ならあなたの力になってくれるはず」
「キーム?」
「ええ。私と同じ、この世界の住人。いつも眉間に皺を寄せているけどとてもいいひとよ」
「きみは?」
「私も後から向かうわ。まだやり残していることがあるから一緒には行けないけれど」
そんな。一人では心細い。できればきみのことを待ちたい。陽介は吐露しかけた本音を寸前のところで押し殺した。ついさっき出会った相手でも、やはり女々しい男だとは思われたくない。
しかしパーチェは陽介の苦悩など全てを見透かしたように笑い飛ばした。
「ふふふ、大丈夫よ。ここの住人はみんな優しいから」
聖母のような微笑みを絶やさないまま、パーチェは西の方角を指差した。その先には一本の砂利道が金色の草木に隠れるようにして続いていた。
「この道をまっすぐ進めばキームの園に行けるわ」
パーチェは聡明だった。路頭に迷う陽介の気持ちを正確に汲み取り、彼のすべきことを即座に提示した。まるでこうなることを前々から予測していたかのように、彼女は完璧だった。とても頼もしかった。
陽介は彼女の言葉を受けて静かに頷いた。漠然とした不安感は残るものの、今は彼女を信じて動くほかにできることはないようだった。決心するように小さく深呼吸する。
「わかった。行ってみるよ」
「ええ。いってらっしゃい」
愛しい我が子どもを見送るようにパーチェが優しく背中を押す。それに促されるようにして陽介は歩きはじめた。
この世界はまるで陽介の知るものとは違っていた。
金色に輝く景色も然ることながら、ここには人どころか虫一匹存在していなかった。風も吹いておらず、まるで時が止まったかのように不自然な静寂が辺りを包み込んでいる。野草や砂利を踏み潰す陽介の足跡だけが異様な程に浮き彫りになっていた。陽介はまだ俄(にわ)かに信じられずにいたが、歩を進めれば進めるほどに、自分が本当に異世界に飛ばされたのかもしれないかと思い始めるようになっていた。
草木をかき分けて進む最中、陽介はふと自分の掌の中に視線を落とした。いつも通り複数の深い皺が彫られてだけであったが、それは以前よりも垢抜けているように思えた。初めて女性に手を握られた。それも飛び切りに美しい女性に。陽介はパーチェに惚れていた。彼女の微笑みを思い出すだけで頬が紅潮した。陽介は力強く拳を握りしめる。手の内に残っている微かな彼女の温もりをいつまでも感じ続けていたかった。
数分歩き続けると、園の終わりはあまりにも唐突に姿を現した。
道や景色が不自然に途切れ、薄く透明な膜が壁のようにして立ちはだかっている。金色に輝く草木の光を受けて、膜はところどころが虹色に染まっていた。見上げるとそれは上空まで続いていて、まるで園そのものが膜に覆われた一つのシャボン玉のようだった。陽介はしばらく辺りを見回した。しかしいくら探しても出口の扉らしきものは見当たらない。
(紲があれば園を移ることができるってパーチェは言ってたけど)陽介は思う。(どうすればいいんだろう)
恐る恐る膜に触れようと手を差し伸べると、刹那、それは陽介を引きずり込むほどの強い力で彼の腕を呑み込んだ。驚き慌てて手を引っ込める。膜を隔てた先は水を内包しているようで、吸い込まれた彼の腕はびっしょりと濡れた。
突然のことに唖然とするも、よく見ると先程パーチェからもらった糸がほんのり光を放って反応していた。
(……?)
もう一度手を透明な膜のほうへ近付けると、その光は強さを増して主張した。まるで陽介をこの膜の向こう側へ導いているようだった。
(ここを突き進めってことなのか?)
不安に駆られ、ふと、後ろを振り返る。しかしもうパーチェの姿は見えない。
陽介は仕方なしに膜と対峙した。やはりここを通り抜けるしか園を出る方法はなさそうだった。
数秒の間考えを巡らせたあと、陽介は目を瞑り、意を決して両手を膜の中に突っ込んだ。膜は彼を受け入れるように力強く陽介の身体を包み込む。そして陽介が抵抗する暇もなく、膜の奥に広がる水中は勢いよく彼を奥へ、さらに奥へと連れ出していった。
暗闇。
瞼の裏を見つめながら、陽介は水の流れに身を任せるほかなかった。先の見えない恐怖が身体を支配する。一体どこへ飛ばされてしまうのか。息を止めながら陽介は数秒前の自分の行動を悔いた。しかし、それも束の間のこと、陽介はすぐに吐き出されるようにして地上に放り出された。着地の姿勢をとることもできず、全身が地面に叩きつけられる。同時に首を激しく反り、脳がグワンと揺れた。
水浸しのまま陽介がゆっくりと目を開けると、先程までいた園とはまるで違った光景が広がっていた。
「わあ……」
陽介は思わず感嘆の息を漏らす。いつかのSFドラマで見たような薄暗い研究室がそこにはあった。暗闇の中、ところどころが青白いライトに照らされて複雑な装置たちが姿を見せている。温かさと抱擁を感じさせたパーチェの園とは違い、ここは叡智と冷たさが充満していた。
陽介が重い身体を持ち上げて立ち上がろうとしたとき、二つの視線が自分に向けられていることに気が付いた。おずおずと視線の先のほうを見る。するとそこには、
「……誰だ、貴様」
全身が機械で覆われた男と、
「あれれ。キミ、見かけない顔だね。どこから来たの?」
中性的な風貌をした少女が一つの空中ディスプレイを囲むようにして立っていた。




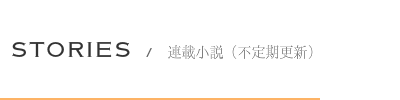
 前話
前話