
第1章「不変で普遍な」 2話
部活を終え、陽介が家路につく頃にはすっかりと夜だった。息が詰まるほど蒸し暑いなか、見飽きた道を一人で歩いていく。道に人気は少なく、ぽつぽつと建つ街灯が仄かに辺りを照らすだけである。
漠然(ばくぜん)とした鬱屈(うっくつ)を抱えたまま腕時計を見ると、時刻は二十時十五分。陽介はこの時間帯に帰宅するのが嫌だった。そろそろ通り沿いの駐車場で不良たちが屯する頃合いだからだ。
その場所が近くなると、闇に染まった木々の間から複数の人影が見えた。三、四人が一人を囲んでいびっている。それはもう見慣れた光景だった。
「おーい、嶋ぁ」
顔見知りの不良がこちらに気付いて手を振ってきた。
無視するわけにもいかず、陽介も小さく手を振り返す。
「お前も一緒にどうだ? 犬っころしか友達がいない笹部くんと仲良しこよししてあげるんだ」
そう言って、不良は一人地面に膝をつける男を指差した。笹部修也、三椏高校では有名ないじめられっ子だった。
「……いや、遠慮しておくよ」
陽介はやんわりと断る。
「何だよノリ悪いなあ」
「そんなことないだろ」
「もうお互い昔のことは忘れてさ、また一緒につるもうぜ。……それともなんだ、また誰かにチクろうとか思ってんじゃねえだろうな?」
ニヒルな笑みを浮かべ、煽るようにして不良は陽介の顔を覗き込んだ。
陽介は修也を横目でちらりと見る。
彼はいつも教室で見せている、怯えた目でこちらを見ていた。もしかしなくてもそれは助けを求める目だった。彼の両腕の中で、どことなく見覚えのある野良犬が唸って威嚇している。
「しないさ」
しかし陽介はその願いを聞き入れない。それを見た不良たちは満足そうに笑った。
「そうか。よかったよかった、お前が良い子ちゃんに戻ってなくて」
陽介は目を逸らした。あからさまに落ち込む修也を見ていられなかったのだ。いたたまれず、小さく「……でも学校では程々にしておけよ。また巻き込まれるのは、その、嫌だし」と、付け加える。
「当たり前よ。お前に迷惑かかることはしねえって」
そう言うと不良たちはようやく陽介を解放した。同級生である彼らの行き過ぎた遊びは学校でも有名で、生徒たちの暗黙の了解になっている。
陽介は安堵の息を洩らしながら、早々にその場をあとにした。いじめを止める勇気はない。だが、決して見ていて気持ちのいいものでもなかった。
帰宅して玄関を開けると、ねっとりとした熱気が一斉に押し寄せてきた。家の中は真っ暗で、いつも通り父親はまだ帰宅していないらしい。
部屋の電気を付け、冷却機のリモコンを探していると突然に携帯が鳴った。
相手は水泳部員からのものだった。
陽介は慌てて再生ボタンを押す。
『おい嶋、聞いたか?』
相手が出たと分かるや否や、水泳部員は突発的に切り出した。電話口からでも分かる焦った声。陽介は何だか胸騒ぎがした。
「どうしたんだよ急に」
『どうしたってお前、飯島の話だよ。聞いてないのか?』
「ハル? ハルがどうかしたのか?」
脳裏には、先ほどまで歯を軋ませていた勝春の顔が浮かんでいた。
『あいつ、今日の練習のあとに部活を辞めるって顧問に言ったらしいんだよ』
「えっ」
『今日のリレー選抜の結果が余程堪えたらしくてさ』
驚く陽介をよそに、部員は続ける。
『前々から辞めたいって言ってたのは知ってたんだけど、まさか本当に辞めるとは思わなくて。なあ、確か嶋って飯島と幼馴染だったよな? お前からも何とか言ってくれよ。せめて一週間後の大会までは残るようにさ』
「ちょ、ちょっと待って。俺、そんな話、ハルから一度も聞いたことがないよ」
すると部員は「ああ」と、どこか納得した様子で呟いた。
『まあそんなとこだろうと思った。飯島ってさ、ちょっと嶋を目の敵にしてるふしがあったし、知らないのも無理ないよ』
その言葉に陽介は狼狽した。全ての時が突然停止してしまったかのような錯覚に陥る。鉛で殴られたように頭の中は突如真っ白になっていた。
(――帰り際にハルが放った「大嫌い」という言葉は本心だったのか)
「それで、ハルが辞める理由はそれだけなのか。それだったら俺がメドレーを辞退すればハルが代わりに……」
『それじゃあ意味ないよ』
「なんで」
『それは……』
部員の奥歯にものが挟まったような口ぶりに、陽介は次第に苛立ちはじめた。
「じゃあ他にも理由があるとか? 部活の雰囲気が嫌だったとか、それとも先輩とうまくいってなかったとか……」
『いや、そういうわけじゃないと思うけど』
「じゃあ何だよ。ハルは誰よりも泳ぐことが好きで、誰よりも熱心に練習していて……」
『嶋』
何かを諭すかのように部員が言う。
『エースのお前には分からないかも知れねえけどな。好きなだけじゃやっていけないこともあるんだよ』
その言葉が何故か異様に重く感じて、陽介は何も言い返せなかった。ただただ押し黙ることしかできなかった。
「へえ。そんなことがあったの」
逢坂彩香は、陽介の話に相槌を打つ。
二十四日の夜も更けた頃。縋るように彼女を電話で呼び出した陽介は、二人、公園のブランコに腰をかけていた。
真夜中の公園は心悲しい。温風に靡(なび)いた葉の重なる音がするだけで、黒々とした闇を照らす街頭は、二人の表情を写すことなく照っている。
「でも陽介くんならすぐ仲直り出来るよ。その、ハルっていう子だって今はちょっとカッとなっているだけで、本当は部活を続けたいんじゃないのかな」
彩香は落ち込む陽介を慰めていた。
「そうだといいんだけど」
「それよりすごいじゃない。二年連続でメドレーリレーの選手に選ばれるなんて。やっぱり陽介くんは浩介と同じで何でもできちゃうのね」
「違うよ。俺はハルがいたから頑張れただけで……」
沈んだ陽介を見て、彩香はそっと微笑んで見せた。
「……そっか。じゃあ尚更ハルくんが早く戻ってきてくれるといいね」
「うん」
陽介より三つ年上の彩香は、彼の兄と同級生だった。別々の大学に進学したあとも密に連絡をしていたようで、たまたま同じバイト先だった弟の陽介にも度々世話を焼いている。
「今日はごめんね彩香さん。こんな夜遅くに突然、相談に乗ってもらっちゃって」
「ううん。最近会ってなかったし、寧ろ会えてよかったよ」
彩香は陽介に優しい。そして陽介はそんな彩香に惚れていた。
すっと通った鼻梁。吸い込まれそうな瞳。耳にかかった髪はやわらかく、彼女の微笑みはまさに聖母マリアそのものだった。
「彩香さん」
陽介は姿勢を正し、口を開く。
「どうしたの?」
「迷惑な話だとは思うんだけどさ、俺、やっぱり彩香さんのことが諦めきれないんだ」
陽介は自分の頬が一瞬にして赤く火照ったのを感じた。手にはじわりと汗が滲んでいる。
「兄貴に比べたら色々と劣る部分はあると思うけどさ、でも、彩香さんを想う気持ちは誰にも負けないから。だからその、あの」
(――言ってしまった)
つい勢い任せに言葉を滑らせてしまった自分を後悔しつつも、陽介は高鳴る胸を抑え、彩香の次の言葉を待った。
暗いこの場所で彼女の表情を読み取ることは出来ない。
少しの間、沈黙が続いた。陽介にはそれが永遠のように感じられた。脈打つ鼓動だけが陽介のなかで響く。
「陽介くん」
ようやく聞こえてきた彩香の声は、絞り出したかのようにか細い。
「何度も言うようで申し訳ないけど、やっぱり私は貴方を恋愛対象として見ることは出来ないわ」
それは三回目のノーの返事。陽介は落胆した。シャボン玉が弾けたような感覚だった。
「……そっか」
「ごめんね」
「い、いや、彩香さんが謝ることないよ。しつこい俺が悪いだけだし」
慌てて彩香の言葉を否定する。性懲りもなく一縷(いちる)の光に縋(すが)っていた自分がひどく滑稽に思えた。
思わず溜息が漏れた。
「俺はいつもこうだ。相手のことを考えずにすぐ自分本位な行動ばかりとって」
ぽつりと呟く。
「陽介くん……」
「だからいつの間にか親友にも嫌われて、好きな子一人も振り向かせることが出来なくて。はあ、なんでなんだろう。俺ってやつはどうしてこう……」
――ばしっ。
刹那。彩香が陽介の頬を引っ叩いていた。
「あ、彩香さん」
「陽介くん。あなた、男でしょう。もっとシャキっとしたらどうなの」
そう言い放ち彩香は立ち去っていた。
じんわりと頬の痛みが広がっていく。
陽介は視線を落とし、一人真っ暗な公園で蹲(つくば)った。




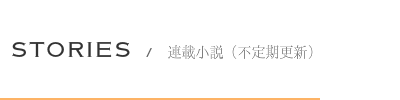
 前話
前話