
第1章「不変で普遍な」 3話
青春、という言葉を口にした瞬間、どうしても自分が自分でないような気がしてしまう。
部活に打ち込んでいても同級生と馬鹿騒ぎをしていても、陽介の心はどこか客観的で、花々しい高校生活を送る周りを疎んじている自分がいた。
何も最初から卑屈だったわけではない。輝かしい青春時代を羨む時期はあった。兄のように友達に囲まれ、先生から信頼を置かれ、美しい女の人を隣に連れて歩くことを夢見ていたこともあった。
しかしいつからか陽介の心は何かが抜けたようにぽっかりと空いていた。
学生の本分が青春を謳歌することだと誰が言ったのだろう。陽介は考える。夢を持ち、理想に憧れ、自尊心に満ち溢れた綺麗事を当たり前のように並べる同級生を見ると、陽介は何だか気恥ずかしい気持ちになった。上辺だけの馴れ合いで充実感を得ようとする浅はかな考え方が、そして虚栄のための、闘争心に燃えた周りの雰囲気が、陽介には悍(おぞま)しく思えてならなかったのだ。
七月三十一日。
結局、勝春は大会当日まで部活に顔を出さなかった。
あれから何度も勝春の家に押しかけては説得を試みたものの取りつく島もなく、とうとう学校構内ですれ違っても避けられるまでの余所余所しい関係に成り下がっていた。
「そう落ち込むなよ。何もお前のせいじゃないって」
見兼ねた水泳部員たちが一様にして陽介を励ます。しかしそれが彼の心に響くことはなく、陽介はすっかりと悄然(しょうぜん)していた。幼馴染と水泳することが唯一の「青春」と呼べるものに近かった陽介にとって、それは何よりも辛い結末だった。
最新設備を整えた県立総合プールは、恐ろしく冷たい雰囲気を感じさせた。
すでに会場では女子百メートル自由形の予選が行われており、折り返しの度にタイムを告げるマネージャーの声が高い天井に木霊した。他校選手の掛け声や声援、水しぶきや電子パネルの音さえもが残響となって陽介の耳にこびりついた。
轟音(ごうおん)。
もう慣れているはずなのに、それは体にのしかかる異様な音圧となって陽介を押し潰す。選手たちがスタートを切るときだけ、しんと静まりかえる光景も何故だか気持ち悪く思えた。
(確か、一年前もこんな気分だったな)
陽介は懐かしむように思う。
毎年この時期の大会は三年生の引退がかかっていて、先輩たちの緊張感や「青春」に対する熱い想いに呑まれつつも、後輩である陽介たちは否応なく疎外感を味わされていた。だけど昨年はそこに勝春もいて、彼と競い合えることだけを楽しみに大会に臨んでいた。
小さくため息をつく。
陽介はどうしても他の同級生と駄弁る気分にもなれず、一人、招集所の端で自分の試合を待っていた。しばらくして顧問が陽介にアップの指示をする。もうすぐ男子二百メートル平泳ぎの予選が始まる時間らしい。陽介は第一組に登場する予定で、本来なら勝春もその隣のレーンで泳ぐはずだった。
「大丈夫? 顔色悪いよ」
マネージャーが生気のない陽介に気がついて、声をかけてきた。
最近夢見が悪く、寝れない日々が続いていたのが体調に影響を及ぼしたらしい。
「……そんなことないよ」
陽介はぶっきらぼうに返す。
「うそ、顔が真っ青よ? あんまり無理しないほうがいいと思うわ。部長と顧問には私のほうから言っておくから、予選が始まるまでもう少し休んでいたほうが……」
「大丈夫だから!」
ぴしゃりと撥(は)ね付ける優しさを突き放すような、小さくも鋭い声。それは『もう俺に構うな』と示唆していた。
「……そ、そう、わかったわ。でもあまり無理はしないでね」
陽介の拒絶を感じ取ったのか、彼女もそれ以上の言及をせずにそそくさと立ち去っていった。あきらかに気分を害しただろうマネージャーを横目で見送りながら陽介は大きな後悔の念に駆られた。
(ああ、俺は何をやってるんだ)
頭を掻き毟(むし)る。
親友には裏切られ、長年想いを馳せていた女にはフラれ、全くもって泳ぐ気分じゃなかった。
重い足取りのまま、係員に導かれてプールサイドのほうへ向かうと、去年も見たような面々が一斉にして陽介を迎えた。威圧するように彼をしげしげと見回す。昨年、一年生でありながら地区代表に選ばれた陽介を目の敵にしているようだった。
「あれ、同じ三椏高校の飯島勝春はまだ来ていないのか」
係員の声に振り返る。
「……彼は体調不良で棄権するそうです」
「ああ、そういえば今朝に連絡が入ってたな。了解」
ただの事務的な会話を交わす。
しかし改めて勝春がいない事実を認識するには十分すぎるものだった。
他校の選手に囲まれ、完全なアウェー感に晒されながらもそれを陽介は気に留めまいと頭を振った。もう何もかもが嫌だった。
「ただいまから男子二百メートル平泳ぎの予選を行います」
プール全体にアナウンスが響き渡る。それを合図に会場は熱狂に包まれた。選手たちの名前が呼ばれ、一人一人が順にしてスタート台の前に立つ。陽介は第三コースだった。
審判長の笛が鳴るのと同時に陽介たちは台に上がり、足をかける。背中を丸めて低い姿勢をとり、身体に力を込める。一瞬、陽介は目眩がした気がした。けれど、もうそんなことはどうでもよかった。
一瞬の沈黙。
生唾を飲む暇もなく、すぐさま銃声が会場を支配する。予選スタートの合図。選手たちは一斉にして入水した。
刹那にして景色は蒼となり、温かい水に包まれ、そこは一人の世界になる。
水泳において、敵は他人ではなく自分とはよく言ったものだ。水をかき分けながら陽介は思う。より良いタイムを出せば自ずと順位はついてくる。要は自分との闘いなのだ。
五十メートルに達したところで、陽介はいつも通り周囲の選手より一歩リードしながら泳いでいた。リズムに乗りながら、徐々にリードを広げていく。しかし、彼の表情はどこか苦しそうだった。
「……なあ、嶋のやつ、何か様子が変じゃねえか?」
「ああ。どうも水に乗れていないみたいだ」
予選を見ていた水泳部員たちも陽介の異変に気付いたようで、招集所では静かなどよめきが走っていた。
二回目のターン時点で、陽介の順位は三位までに落ちていた。どんどん失速し、他の選手にも少しずつ引き離され始めていた。
(あれ、おかしいな)
水のなかで陽介は思う。
蒼の世界に黒い影が二つ、左右の端に写っていた。
泳いでも泳いでも追いつかない。たちまちのうちに影はみるみると小さくなっていく。陽介だけが水の中で一人取り残されていた。それは今まで見たことのない光景だった。
(こんなはずじゃ、なかったんだけどなあ)
陽介は心の中で呟く。不思議と焦っていない自分に驚いた。
苦しかった。息がいつも以上に切れていた。いつも泳いでいるはずの二百メートルが異様に長く感じた。
最後の十メートル、ゴールが見えてきた頃、陽介の意識は朦朧としていた。
視界が霞み、呼吸するたびに走る水の衝撃が脳味噌に響く。陽介は必死で泳いだ。頭が痛い。吐き気がする。だけどあと少し。あともう少しで、この苦しみから解き放たれる。そう自分に言い聞かせながら重い手足を懸命に動かした。
二重にも三重にもなった景色をどうにか掴み取ろうと手を伸ばした瞬間、陽介の視界が百八十度回転した。
遠くて人が叫ぶ声がする。
ぐらぐら。ぐらぐらぐら。
陽介の意識は、いつの間にか暗い水の底へと沈んでいった。




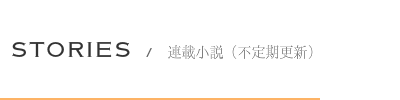
 前話
前話