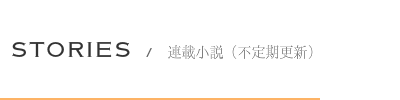第1章「不変で普遍な」 1話
校内放送で嶋陽介の名前が繰り返されたのは、陽が沈みかけた七月二十四日のことだった。
夏休みを迎えて一週間が経つ三椏(みつまた)高等学校には相も変わらず多くの生徒で溢れていて、朗らかとした、横溢の活気が校舎を包んでいる。
陽介は同じ水泳部員と一緒に校内プールで泳いでいた。練習最後に行うタイム測定を終え、校内中に響き渡るその呼び出しアナウンスに一種の呆れを感じつつも、陽介は水から上がり練習を抜ける。濡れた髪のまま職員室に顔を出すと、担任教師の磯貝の嫌味ったらしい顔が彼を待ち構えていた。
「何で呼び出されたか分かっているよな」
低い声で先生が生徒に問う。
「……はい」
「また課外授業をサボったそうじゃないか。伊吹先生が怒っていたぞ、あいつは全く聞き分けがなってないって」
「すみません」
陽介は素直に頭を下げる。下手に言い訳をすれば磯貝の小言がうるさいのは学校で有名だっだ。ねちょねちょと汚い口を動かして話す彼を見ていると、陽介は無性に苛立った。
「水泳部の大会も近いし、練習に集中したいのは分かる。でもだからといって勉強を疎かにしていい理由にはならないんだ。分かるよな?」
「はい」
「今の成績のまま進級してみろ、来年の大学受験で自分の首を絞めるだけだぞ」
ばんっ、と、そう言って磯貝が机に叩きつけたのは陽介とその兄、浩介の成績表だった。
「大体な、お前は学生の本分が勉学である事をまるで分かっていない。これを見ろ。お前の今の成績と、お前の兄が高校二年生だった頃の成績だ。差は歴然だろう」
まただ、と陽介は思う。職員室に行けば必ずといっていいほど兄の話を持ち出され、そして比べられた。それは兄が三椏高校で唯一T大学に合格したという実績を残したからであって、必然的に同様の期待が陽介の肩には重くのしかかっていた。
「なあ、お前も少しは浩介を見習ってみたらどうだ。兄にやられっぱなしじゃあ悔しいだろう。お前も少しは良い大学に進学したいだろう」
「はい」
「とにかく夏休み明けの定期考査までに各教科十点は上げるんだ。特に一番点数が低い古典」
「はい」
「明日からはちゃんと伊吹先生の課外授業に出席して、分からない部分をしっかり復習しろ。いいな」
「はい」
淡々と、機械的な返事を繰り返しているうちに磯貝はとうとう観念したのか「もういい。下がれ」と言って陽介を追い返した。
職員室を退出すると同時に奥の方から聞こえてくる、教師たちのひそひそ話。
「今の生徒は?」「嶋浩介の弟らしいわ」「兄弟って案外似ないものね」「兄はあんなに優秀だったのに」「あいつはもったいなかったよなあ。これからって時に」
陽介は振り切るようにしてその場を後にした。これ以上、この重い空気に耐えられないと自分の身体が叫んでいたのだ。
「まーた先生に説教されてたのかよ、陽介」
部活に戻ると、プールサイドでタイム測定を手伝っていた飯島勝春が近づいてきた。スイミングスクールから付き合いがある二人は、同じ平泳ぎを専門とする良きライバルでもあった。
「別にいいだろ。ほっとけ」
そう言って肩に置かれた勝春の手を振りほどく。
「そもそも何でお前はこの時期の課外授業に申し込んだんだよ。大会が近いから出席できないのは分かりきっていたことだろう」
「知るかよ。磯貝が勝手に申し込んだんだ。俺じゃない」
「ははは。あの先生が。そりゃあ御愁傷様だな」
勝春が乾いた笑いを漏らす。不自然だった。誰が見てもわかるほどに、彼の顔は強張っていた。
「緊張してるのか?」そう陽介が質問した途端、勝春の表情が曇る。
「……当たり前だろ。今日でリレー選抜のメンバーが決まるんだぜ。もしかしたら今日のタイムで全てが変わるかもしれない」
低い声で返す。
勝春は異常なまでにメドレーリレー選抜に執着していた。それは水泳部代表になることで優越感に浸りたいからなのか、それともただ単純にメドレーリレーに出場したいだけなのか、陽介には分からない。勝春と違い、陽介は泳げさえすればなんでもよかった。
「まあでもハルならきっと大丈夫だよ。俺なんてさ、最近はめっきり調子が悪くて……」
「待て、これ以上は何も言うな。今日の手応えを聞くのはメンバー発表のあとだ」
陽介の言葉を遮り勝春は言う。
「それまではお互い練習に集中しようぜ」
「あ、ああ」
「……負けないからな」
一方的に会話を終わらせ、対抗心剥き出しにする勝春。そんな態度に内心気圧されつつも、陽介は気にかけまいとストレッチを始めた。
昨年、メドレーメンバーに選抜されたのは勝春ではなく陽介だった。
通常練習のあと、顧問が部員全員を集めた頃には日もすっかりと落ちていた。
「全員、ご苦労さま」顧問は浮き足立った部員一人一人の顔を見ながら話す。
定型的に活動の締めの言葉を並べたあと、改めて二週間後の大会について触れた。
「いいか、大会はもう目前だ。今日の記録を見る限り、タイムが伸びている奴が比較的多いようだが、安心するのはまだ早い。無理はしないように、だけど最後まで気を抜かないようにな」
全員が勢いよく返事する。満足した顧問は手にしたバインダーに視線を落とし、
「よし。じゃあ今からメドレーリレーのメンバーを発表する」
と、告げた。
一瞬にして部員たちの間に緊張が走る。表情の硬い勝春の生唾を飲む音がした。
一人、先輩の名前が呼ばれる。
一喜一憂する部員たちを見ていると、何故だか陽介もつられて手に変な汗を掻いてしまう。
一人、そしてまた一人。
まだ二年生の名前は呼ばれない。勝春はまだかまだかというように、落ち着かない様子で貧乏揺すりを始めた。
そして最後に呼ばれたのは、
「一年の嶋陽介、以上四名だ」
陽介の名前だった。勝春は昨年と同じく補欠だった。
「いま呼ばれたレギュラーメンバーはこのあと話があるから少し残っていくように。では解散」
顧問の言葉で部員たちはぞろぞろと帰り支度を始める。そんななか勝春は笑顔で陽介の背中を叩き激励した。
「良かったじゃん、陽介。これで二年連続出場だな」
「あ、ああ」
「でも平泳ぎのほうじゃ負けねえから。しっかりニコメのほうも練習しておけよ」
「ハル、俺は……」
「おいおい何でそんな弱気なんだよ。自信持てって。なんて言ったって、お前は二年で唯一のメンバー入りだからな」
えらく饒舌な勝春にどう応えればいいかわからず陽介がしどろもどろになっていると、
「……そんな顔するなよ」勝春が小さく零した。そこに先程までの笑顔はなく、拳は強く握りしめられている。
「ハル」
「いいよな、お前は。大した努力もしてないくせにいつも俺の先をいってさ。小学生のときからそうだ。練習のときはいつも俺のほうがタイムは良いのに、いつも俺のほうが練習しているのに、試合になるとすぐ追い抜かれる」
濡れそぼつ勝春は、まるで溺れかけた子犬のような目をしていた。
「陽介。俺はずっとお前のことが大嫌いだったよ」
そう吐き捨てて部室を飛び出す勝春に、陽介はなんと声をかければいいのか分からなかった。