
第1章「祭」 3話
「いやあ。腹が減って力が出なかったもんだからさ、助かったよ。あ、これ店に並んでた作り置きを勝手に持ってきちゃったんだけど大丈夫だった? ……それにしてもこれ、美味いね。今日初めて食べたんだけどさ、何、ここらへんじゃ有名なの?」
呑気に喋り続ける盗人をただ唖然として見つづける勝茂。
それを訝(いぶか)しんだのか、盗人は近付いて「どうしたんだよ黙っちゃって、俺の顔に何か付いている?」と彼の顔を覗き込んだ。
「お前は……さっきの」
震える声を抑え、勝茂はどうにか言葉を発する。
「嗚呼。もしかして君、さっき小銭をばら撒いた場所に居た?」
盗人は思い出したように尋ねた。
「ああ。いたけど」
「いやあ面白かったよね。見た? あの代官の怒り狂った顔。今思い出しても笑えてくる」
くっくと肩を小刻みに震わせながら盗人は笑ってみせた。
「お、面白いわけがないだろう! あの代官様を怒らせたんだぞ、きっとただじゃ済まされない」
「そうかもね」
「しかも何でお前が家(ここ)で呑気に寛(くつろ)いでいるんだ。それにどうしてお前みたいな異国人がこの国に入ってお代官様に喧嘩を売るような真似を……」
「ははは。ないしょ」
盗人は終始あっけらかんとしていた。何を言われても焼きそばを食べる手を止めない。なにより彼の目尻を下げた笑みが緊張感を失わせた。
しかし、同時に何かを見透かしているように思えて気味が悪かった。
「君、異国人に会うのは初めてだろう?」
突然、盗人が言う。
「だったらなんだよ」
「別に。君、さっきから怖い顔で俺を見るからさ」
「当たり前だろう。誰が家に不法侵入した泥棒と仲良くなれるかってんだ」
「ははは。それもそうか」
まったく悪びれる様子もなく頷く。
よく見れば盗人は勝茂よりも幼く、小柄な少年だった。まだ母親に甘えていてもいい年頃のようにも見える。
(本当に、この餓鬼は何をしに来たんだ。)
勝茂は思う。鎖国状況にあるこの国に浸入するなど、只事ではない。
外では未だに奉公人たちの荒々しい足音と緊迫した声が飛び交っていた。
「騒がしいなあ」
まるで他人事のように盗人は呟いた。
「逃げ切るつもりなのか?」
勝茂が尋ねる。
「もちろん」
「大した自信だな」
「まあ君が最後まで誰にも言わずにいてくれたらの話だけどね」
「へえ、俺を信用しているのか」
「うん。もし助けを呼ぶならとっくに呼んでるだろうし」
「……」
勝茂は咄嗟(とっさ)に返す言葉が出てこなかった。
確かに目の前にいるのは悪党だ。しかし彼の瞳に映っているのは一人の少年のあどけない笑顔だった。貧しい町人らに小判を分け与えた彼を罪人だと斬り捨てるのはなかなかどうして煮え切らない。
押し黙る勝茂を見て、盗人はにんまりと口角を上げた。
「君は正茂と似て優しいね。だけどもうちょい用心したほうが身のためだぜ。俺なんかより怖い強盗は外にウジャウジャいるから」
正茂――盗人が突如、口にした名前。
「な、何でお前、親父の名前を……」
勝茂は戸惑った。しかし、そんなことなどお構いなしに盗人は立ち上がる。
「あ、おい」
「さあて、上手い飯も食えたしそろそろ行くとしますか」
盗人は大きく背伸びをすると、さっさと戸口のほうへと向かって歩き出す。見れば、彼が持っていた皿からは綺麗さっぱりと焼きそばが消えていた。
「おい、待てって」勝茂は慌てて彼の肩を掴んだ。
「何?」
「お前、親父の知り合いなのか?」
「ひみつ」
盗人は口を割らない。
勝茂はそっと溜め息をついた。
「……もういい。こっちだって面倒事は御免だ、無理に深追いするつもりはない。だが払うもん払ってから出ていけよ」
「え?」
「え、じゃない。タダ飯をあげる気はさらさらないからな」
盗人が完食した皿を指差し、右手を差し出す。
すると盗人は苦虫を噛み潰したような顔で勝茂を見上げた。
「えー勘弁してくれよ。いま一文無しなんだよ」
「嘘つけ」
「嘘じゃないさ」
「だってさっき大量の小判を撒き散らしていたじゃないか」
「あれで全部だよ。もうここには何も残ってない」
そう言って盗人は腰に巻きつけていた巾着袋の中身を勝茂に見せる。空っぽだった。
「本当に一文も持っていないのか?」
「うん」
自信満々に頷く盗人を見て勝茂は唖然とした。
「お前、この国に何しに来たんだよ。大罪を犯してまで盗んだ小判を全てばら撒くなんて。これじゃあただの骨折り損じゃないか」
「いいや、それがそうでもないんだな」
そう言って盗人は懐から一枚の藁半紙を取り出した。何やら細かい文字や数字が記されている。
「何だそれ」
「この藩の納税記帳」
「まさかそれも代官様から盗んできたのか?」
「ご名答」
「何のために」
「あの悪代官を引きずり下ろすためさ。あ、そうだ、君も一緒にどうだい?」
「はあ? どうして俺が……」
唐突の申し出に勝茂は馬鹿馬鹿しい、と鼻の先であしらう。しかし腹に一物を抱えていそうな盗人の笑みに一瞬、悪寒が走った。
「この納税記帳さえあれば、あの代官の悪事を白日のもとに晒すことができるんだ。どうだ、興味あるだろう? 憎き悪代官に赤っ恥かかせることができるんだぜ」
紙をこちらにちらつかせながら盗人は続ける。
「俺もさ、ああいう外道は見過ごせない性分だからよく分かるよ。自分たちのお金があんな奴に乱用されるなんて許せないよね。こっちは毎日生活を切り詰めないと年貢も払えないっていうのに、お代官様といえば人の上であぐらをかきながら呑気に豪遊三昧。しかもそれが元家臣ともなると感情も一塩だよね」
「おい、急に何を言い出すんだ。俺は別に何も……」
「いいんだよ、隠さなくて」
意味深長な笑みを浮かべたまま、盗人は続ける。
「俺は別にこそ泥して呑気に他所の家で食事するために東雲国(ここ)に来たわけじゃない。君たちを助けるために来たんだ」
「何のために。第一、俺とお前は初対面のはずだろう。助けられる筋合いがない」
「いいや、それがそうでもないんだな」
そう言って勝茂の肩を力強く掴む。
「小判なんてほんの前座さ、三重勝茂。今宵の祭りの主役は君なんだよ」
「……」
勝茂は再び開いた口が塞がらなかった。




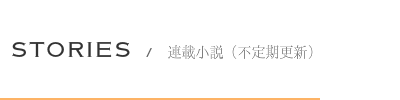
 前話
前話