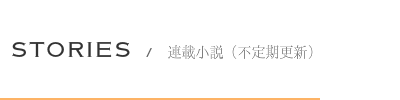第1章「祭」 1話
町は宵にも関わらず、かつてない賑わいを見せていた。
狭い参道には屋台が連なるように並び、人々の高揚したざわめき声が飛び交っている。耳を澄ませば遠くから祭囃子が聞こえ、辺りに舞う香ばしいソースの匂いが人の食欲を刺激した。さすが年に一度の祭りなだけあって露天商の気合も上々なのだろう、店主が子供たちを言葉巧みに誘い込んでは商物を売りつけていた。
その数ある屋台のなかで、ひっそりと焼きそばを作る親父の姿が見えた。あまり繁盛(はんじょう)はしていないようで、孤独にせっせと麺を混ぜる姿がとても物寂しい。
「親父、焼きそば一つ頂戴」
俺がそっと近寄り声をかけると、
「……勝茂か」
親父は客として訪れた息子に対し、ぶっきらぼうに返事をした。そして無言のまま額に滲んだ汗を拭き、鉄板に油を引く。まだ商品は沢山並べられているのに新しいものを作ってくれるのが親父らしい。無骨な人参やピーマンが入ったそれを不器用にかき混ぜては器に装い終えると、親父は二人分の夕飯を差し出した。
「親父も食うの?」と問えば「当分客も来ねえだろうから」と答える。それは実にそっけない態度だった。
華やかな祭りの路上で、俺たち二人は静かに腰を下ろす。
見上げれば煌びやかな花火が空を彩り、皆が陽気な音楽に合わせて歌い踊って今日という日を満悦している。
「賑やかだね」
「そうだな」
しかし親子に流れる空気はどこかぎこちなかった。言葉を一つ二つ交わせば、たちまち気まずい静寂が辺りを包み込んだ。
俺は親父の作った料理が何故だか好きだった。
湯気立った焼きそばは、見てくれこそ悪いものの濃厚な美味しさと香ばしさを与えてくれる。俺は口に含んだ麺をゆっくりと噛みしめ、その味を惜しむかのように飲み込んだ。その動作が無性に俺を幸せにさせた。
「……こんなに美味いのに」
俺がぽつりと呟くと、親父はいつになく弱気な笑顔を浮かべた。
「他にも焼きそばを売っている店はあるからな。形が悪いと誰も買いたがらねえんだろう」
自分の店の不人気さを気にしているのか、親父は自嘲気味に言って見せた。
暫く黙々と焼きそばを食べる時間が続く。箸で麺をつまんでは味わい、また箸で麺をつまんでは味わい。たちまち二人の皿は空っぽになっていった。
御袋が死んでから数ヶ月が経った今。親父は明らかに覇気を失くしていた。口数も減り、どこか自閉気味な親父を見るのは物悲しい。しかしそんな親父が突然屋台を出したいと言い出したのは、祭りを楽しみにしていた御袋の面影を追うためだろう。最期の年まで縁日に屋台を出し続けていた御袋は誰から見ても輝いていた。御袋との日々を想うように、必死に、汗水垂らしながら料理するその背中は何とまあ小さいことか。
今、白髪は煌びやかな神輿をぼんやりと眺めている。
俺には親父が何を考えているのかは分からなかった。ただ、その瞳はどこか寂しげだった。
ドロボウだあー。ドロボウだあー。
しばらくして遠くの方から人の金切り声が聞こえてくる。
祝いの場に似つかわしくない声に誰もが顔をしかめたが、それは一瞬のことで、特に気に留める者はいない。
しかしその音は次第に大きくなっていく。
ドロボウだあー。ドロボウだあー。人の咆哮(ほうこう)する声がする。
刹那、それに混ざってガラスが破れる音がした。驚き慌てた親父と俺は立ち上がり、辺りを見回す。
「ねえ、あれ」
近くで、何かに気づいた子どもが上を指差した。釣られた通行人らが一斉に空を見上げる。
そこには小男が一人、巨大な袋を抱えて屋敷の屋根の上を走っていた。
そのすぐ脇で上等な着物を羽織った代官が窓から身を乗り出し、「このドロボウめ! 逃がすものか!」と叫んでいる。どうやら祭りに便乗した輩が盗みを働いたらしく、騒ぎを聞きつけた奉行所の者たちも駆け寄ってきていた。
「……ありゃ異国のモンだな」
隣で親父が小さく呟いた。
確かによく見れば、盗人は見たことのないような風貌をしていた。緑色の髪。着物でも甚平でもない不思議な服。全身を布で纏ったそれは見るからに動きづらそうだった。
小男は盗品をやっとの思いで代官から引き離すと、満足そうな笑みを浮かべてこちらを見下ろしてきた。
(――何を立ち止まっているのだろう。逃げる気がないのだろうか。)
そう思った矢先、なんと男は逃げるどころか声を張り上げて、
「やあ諸君! 今宵は祭りらしいな!」
と、こちらに話しかけてきたではないか。
何事だ。一体あいつは何者なんだ。戸惑い騒めく俺たちの気などお構いなしに、盗人は続けて語り始める。
「いやあ、これほどめでたい日はない! さあ皆の衆、今日という日を共に祝福しようではないか!」
盗人はそう言って、あろうことか自分が盗んだ大量の小判を地上に放ったのだった。
金が空から降り注ぐ。その異様な光景を誰が予想していただろうか。
悲鳴をあげる代官とは裏腹に、町人らは驚きつつも感嘆の声を上げ、地上に落下した小判を無我夢中で拾い集め出した。
俺と親父は呆気にとられていた。